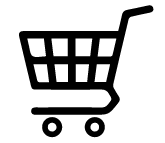江戸時代から栄え北海道を豊かにしたニシン漁。しかし1950年代に入ると漁獲が激減し、大きな転機を迎えました。先代社長 井出喜規は、新たな原料をアラスカ、カナダに求めて産地開拓を行いました。
その当時、アラスカ、カナダでは数の子はおろかニシンすら食す文化がなかったため、現地の漁師にニシン漁を指導することからスタートさせました。井出や道内大手各社の先代の方々が先頭に立ち、やがて北米での数の子事業は日本向けの輸出産業として順調に発展。
その後、井出は次なる産地としてロシアに目を向けたのでした。
数の子メーカーとしての誇り
ニシンを求めて
新しい時代に向けて
かつて「黄色いダイヤ」と呼ばれ、お正月やお祝いの席に欠かすことのできなかった数の子。数の子買占め事件が日経新聞の1面記事になったこともあるなど、高値のイメージが定着していました。
しかし1970年代には、「おせちもいいけどカレーもね!」というキャッチコピーが生まれるほど、お正月の過ごし方や数の子の消費をめぐる環境は時代と共に大きく変化していました。
また、ピーク時は240社あったといわれた北海道内のメーカーが40社程度に減少するなど、他の水産商品と同様に衰退・縮小の道をたどっていました。
そんな中、井出は加工地として中国の存在に早くから着目し、質の良い水が豊富にある青島でニシン加工拠点の整備を進めました。それは、それまで淡水の魚を食していた中国市場に安くておいしいニシンを通じて海の魚を知らしめ、新たな市場創出にも繋がりました。
日本、ロシア、中国間の地理的な近接性は、北米産ニシン事業にはない産地・加工地・消費地を柔軟に組合せる新しいモデルとなり、井出の下で数の子事業の経験を積んだ多くの人材はやがて独立し、このモデルに拠る新たな数の子産業を発展させていきました。
生産一貫体制の確立
2000年、前社長が会長へ、そして長男の井出敬也が社長に就任しました。異業種での経験から「数の子屋の常識は世の非常識、世の常識は数の子屋の非常識」と考え、手軽に買える価格帯の商品を販売したりスーパーが店頭に並べたい商品をつくるなど、これまで業界になかったいくつものマーケットインを行い全国に向け販売を起点とした経営改革に着手。量販店との取引を拡大させていきました。
2012年には北海道岩内に工場を取得。産地で買い付けし国内で加工、最終製品製造までを一貫して行える体制を整えました。あえて岩内に工場を持つことは、数の子産業の次世代の人材育成やニシン文化を持つ北海道に根を下ろすことで、ニシンで複層的な事業を行う新たな構想のためでもありました。女性も多く活躍する岩内工場は、80代でお元気に働く方や母娘二代で勤める方、ベトナムからの技能実習生などに支えられ、一年中忙しく稼働し続ける工場へと成長していきます。
産業再編のとき
2010年代、数の子業界は産地の漁獲減、日本市場の消費減、産地の漁業者・国内メーカーの利益減という3つの減少に直面します。数の子最大の産地であるカナダ、アラスカは漁獲の波が大きく、北米各産地では小型化が進み資源の枯渇をうかがわせるようになります。
消費の減少を現地の価格引き下げで乗り切ろうとしますが、操業コストは上がり続け2020年では大手の2社が不採算を理由に操業を見送る事態にもなりました。新型コロナウイルスの影響と合わせ最大の産地であったトギアックは「9割減」という未曾有の落ち込みも見せました。
数の子は日本にしか市場がないにも関わらず原料のほとんどを海外に依存するという特殊な商品です。それだけに産地と消費地のかかわりは深く、それぞれの疲弊は業界だけでなく産業そのものを再編する局面にいたりました。
一方その間、ロシアでは新たな動きが起こります。
国内にニシン市場があるロシアでは、オスはロシアや近隣の中国へ販売しメスは日本に高値で販売し収益化を図る構造が定着していました。
当社はロシアの漁業者とのパートナーシップを結び、網船の導入や設備投資に協力することで安定的な仕入れ体制を構築。漁で収穫した魚を全量買い取り、産地が生産に集中できるよう協力を続けました。
その方法はときに供給過多を引き起こすため、より多くの数の子を販売できるよう細やかな商品企画とマーケティングにも力を入れ、それまで業界になかった新しい商品をどんどん市場に投入していきました。その結果、販売数を伸ばし、採用する店舗は年々増加、産地にはさらなる生産能力の強化がなされていくことで産地メーカーと当社が正のスパイラルを作りだしました。
これにより、日本国内では高品質かつ漁獲が安定した産地としてロシア産数の子の認知が高まり、北米産ニシンを代替する産地へと成長を遂げたのでした。
新年最初の食卓を彩る
矜持
このように数の子産業の歴史に深く関わってきた当社は、数の子事業に格別なる思いと愛情をもって取り組んでおります。これをロシア側からみれば、当社との取り組みが日本の数の子産業の写し絵であります。
今や当社は日本で唯一の現地での原料買付から腹出し、原卵加工、販売までを一貫して行う数の子メーカーとなりました。 このマーケットリーダーとしての、そして日本の新年最初の食卓を彩る数の子メーカーとしての矜持をもって日々事業に取り組んでまいります。